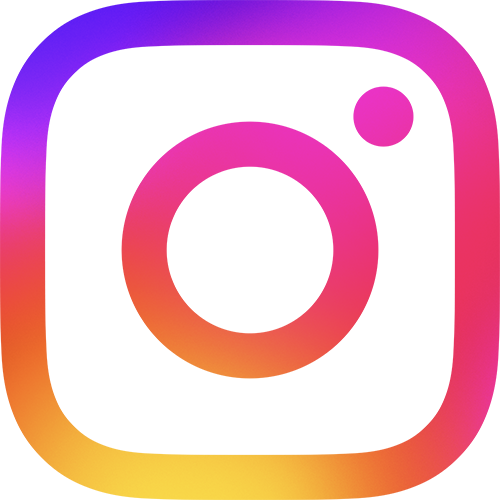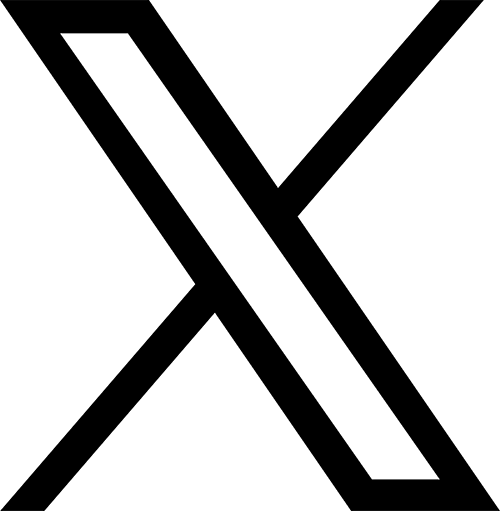一般社団法人日本観光文化協会(東京都北区赤羽西1-22-15:会長 小塩稲之)は、今年で7回目になる、全国の観光特産品の知名度・ブランド力向上を目的とした観光特産品の表彰制度「日本観光特産大賞」のノミネート15品を発表します。
「日本観光特産大賞」(https://jtmm.jp/award/)とは、毎年12月に一般社団法人日本観光文化協会が、食と観光、地元グルメ、お土産品などでその年話題になった観光特産品を表彰してゆく制度です。「日本観光特産大賞 グランプリ」「金賞 優秀賞」「金賞 ニューウェーブ賞」発表に向けて、一般社団法人日本観光文化協会会員によりノミネートされた観光特産品の中から、当協会専門委員会によって15品に絞られました。
この活動の目的は、日本各地で育成されている観光特産品を再発見、再発掘し、一定の価値を付与することで、知名度やブランド力向上に寄与し地域の活性化を後押しすることです。また、協会では表彰された観光特産品の時代背景や社会的な価値などを今後も調査分析し、内外に発信をしてまいります。最終選考では7名の専門家が審査員となり、ノミネートされた特産品に1位から15位までランキングを付け、ポイントによる加点方式で集計し「観光特産大賞 グランプリ」「金賞 優秀賞」「金賞 ニューウェーブ賞」を決定してゆきます。
※注 当協会において「観光特産」とは、「観光資源と地域特産の融合によって生み出された商品及びサービス」のことで、「観光特産=観光資源×地域特産」という公式で定義しています。
▼ノミネート品詳細
◆ほたて貝(北海道) 猿払のほたてはオホーツクの天然貝。ほたての水揚げで日本最北の村『猿払(さるふつ)』で取れるほたては、厳しい天然の環境で稚貝を撒き、4年をかけて育てられます。
◆バター餅(秋田)バター餅は北秋田市の阿仁地区を中心に食べられてきた家庭の味。狩猟を生業とするマタギが山に入る際の保存食が起源とも言われています。今では北秋田市を代表する特産品となっています。
◆莫迦焼締(ばかやきしめ)(宮城)宮城では独特な味わい深い温もりが伝わる台ヶ森焼が備前焼・丹波焼・萩焼きなどを合わせたような焼物として親しまれています。その中で震災復興時に誕生した莫迦焼締は、水洗いすると色が変わる不思議な陶器で、製作日数が一年以上かかる、貴重なものです。
◆幸生牛(さちうぎゅう)(山形)山形県寒河江(さがえ)市という地域の文化や歴史を感じることができる幸生牧場の自然豊かな環境で育つブランド牛の幸生牛は自然の恵みを受け継いで育ち、生産・加工・販売・小売り・外食の一貫した6次化産業のモデルにもなっています。
◆日光湯波(栃木)日光湯波(ゆば)は日本の「ゆば」の二大産地として知られる伝統ある日光の名産品。「ゆば」は良質のたんぱく質をはじめ、カルシウムや鉄分の量も多く、低カロリーで消化もよいとして精進料理には欠かせない食材です。
◆八丁味噌(愛知)八丁味噌は米麹や麦麹を用いず、大豆の全てを麹にした豆麹で作られる豆味噌の一つ。愛知県岡崎市八帖町・八丁町で江戸時代初期から造られています。毎年、地元味噌蔵から成る「八丁味噌協同組合」が主催する秋まつりが開催されます。
◆白えび(富山)白えびは「富山湾の宝石」と称される希少な海産物で、その透き通った美しさと上品な甘みが特徴。地元では白えび漁観光船で臨場感あふれる白えび漁の見学や獲れたての透明に輝く白えびを味わうことができます。
◆加賀棒茶(石川)お茶の木の上質な茎の部分を焙煎して作られる加賀棒茶は、芳ばしい香りと自然な甘味が特徴。茶は江戸時代から藩内で贅沢品として生産されていましたが、多くの人が楽しめるように茶の茎を焙じて炒った「加賀棒茶」が広く普及しました。
◆敦賀おぼろ昆布(福井)古くから日本海側物流の拠点港として栄えてきた敦賀の主要な荷揚げ品の一つが北海道の昆布。継承されてきた昆布の加工技術に光をあてることで、港町の歴史文化を象徴する産業として文化継承や人材育成、地域活性に役にたっています。
◆京野菜(京都)京野菜は、京都の土と気候で育まれ、栄養的にも優れた野菜として京の食文化を支える重要な食材。古来より旬の季節のその土地で穫れるものを食するのが理にかなっていて健康に良い、という原点を大切に、伝統を守り、さらに発展させていくための事業に取り組んでいます。
◆すだち(徳島)すだちは元々徳島県で自然に生じた果物であり、江戸時代から栽培されてきました。1960年代には商業的な栽培が本格化し、現在では全国のすだち生産量の約90%以上を徳島県が占めています。県花にもなっていて、地域の文化や食文化に深く根付いています。
◆鰹のたたき(高知)かつおは古くから土佐人に愛されてきた魚で、高知県の県魚としても知られています。鰹のたたきは “焼き切り”と呼ばれ、5枚におろして節にしたものを表面だけさっとあぶり、まな板に乗せて塩を振ってたたきにする料理です。
◆元祖地獄蒸しプリン(大分)別府の温泉蒸気を使った地獄蒸しは、この地域独自の伝統的調理法。地域資源と食品文化の融合の象徴として作られ、地元産素材を用いた無添加のプリンは温泉由来のミネラル風味が特徴。プリンと観光の地獄蒸し体験と融合した地域観光との相乗効果も創出しています。
◆かごしま黒豚(鹿児島)かごしま黒豚のルーツは、今から約400年前、島津18代藩主・家久により琉球から鹿児島に移入されたといわれます。さらに幕末には水戸藩主徳川斉昭公に「いかにも珍味、滋味あり」と言わしめ、郷土の偉人・西郷隆盛もこよなく愛したといわれています。
◆名護市パイナップル(沖縄)糖度の高いパイナップルの生育には酸性の赤土で非常に水はけのよい土地、気温30度~35度の高い夏、という条件が必要です。パイナップルの生産量日本一の沖縄でも本島北部と石垣島の限られた土地でしか栽培ができません。また、パイナップルの観光テーマパークで楽しんでいただけます。
昨年2024年は、「福岡県:玄海もん(玄界灘の魚介)」が観光特産大賞「グランプリ」を受賞しました。また、「高知県:こけらずし」が「金賞 優秀賞」を、「千葉県:コーヒー『プリンス徳川カフェ』」が「金賞 ニューウェーブ賞」を受賞し、地方紙などのメディアに掲載されるなど話題になりました。
<日本観光特産大賞>
◆審査方法:一般社団法人日本観光文化協会会員によりノミネートされた品を当協会専門委員会による選で
15品に絞りこみ
◆最終選考:審査員によるランキング付け・順位を数値化し集計
審査員(敬称略):日野 隆生(元東京富士大学教授) 舘 和彦(愛知学泉大学教授)
笠谷 圭児(経済産業省認可セールスレップ・販路コーディネータ協同組合副理事長)
金廣 利三(6次産業化プランナー) 槙 利絵子(観光特産士マイスター・観光コーディネーター)
植田 聡子(観光PRコンサルタント、JTCC認定観光コーディネーター、日本観光士会認定講師)
小塩 稲之(日本観光文化協会会長)
◆スケジュール:最終選考 2025年11月末
【主 催】 一般社団法人 日本観光文化協会
【運 営】 全国観光特産士会 運営事務局

配信元企業:一般社団法人 日本観光文化協会
プレスリリース詳細へ
ドリームニューストップへ