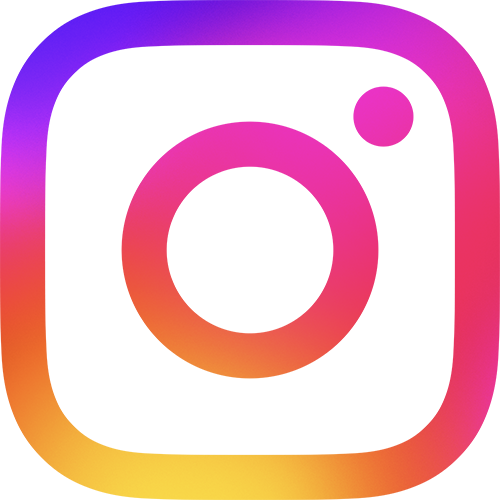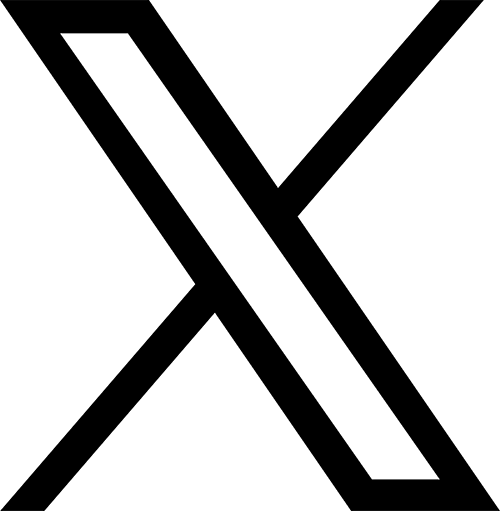2018年度から10年間の時限措置として、事業承継を後押しする税制上の特例である事業承継税制が拡充されています。自社株の贈与や相続にかかる税負担を大幅に軽減できるので、中小企業の事業承継ではぜひ利用を考えたいものです。
ただし、長期的な視点で利用しないと、デメリットが生じる可能性もあります。新しい事業承継税制の概要と上手な利用ポイントを整理してみます。
※本稿は事業承継税制のアウトラインを分かりやすく説明することを目的としており、実際の利用にあたっては税理士等の専門家にご相談ください。
事業承継税制のメリットとデメリットとは : https://100years-company.jp/articles/inheritance/040046
1.事業承継税制とは?
事業承継税制とは、中小企業の経営者から、後継者が会社の株式を贈与や相続で引き継ぐ際に、本来支払うべき贈与税や相続税の納税を猶予する制度です。猶予された税金は、一定の条件を満たせば将来的に免除されます。すなわち、中小企業の事業承継がスムーズに進むよう、自社株の移転について税制面からバックアップする制度といえるのです。
2009年(平成21年)度税制改正において、事業の後継者を対象とした「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」(経営承継円滑化法)が制定され、これに基づく「非上場株式等に係る相続税の納税猶予制度」が創設されたのが、事業承継税制の始まりです。
当初は要件が厳格で、なかなか利用件数が伸びなかったため、2013年(平成25年)度から一部、要件が緩和されました。事業承継後、従業員の雇用の8割以上を「毎年」維持という要件については、「5年間平均」での評価がされることになりました。また以前までは、先代経営者は贈与時に役員を退任しなければなりませんでしたが、有給役員としての残留が可能となりました。さらに後継者の対象を現経営者の親族に限定していましたが、その対象を親族以外にまで広げ、後継者の引受け手の拡大を目指したのです。
そして2018年(平成30年)度の税制改正により、時限措置として抜本的な拡充が行われました。これが特例措置と呼ばれます。従来からの一般措置も残っていますが、特例措置のほうが大幅に利用しやすく、メリットも大きくなっています。
2.10年限定の特例措置はここが拡充された
事業承継税制の特例措置は、一般措置に比べてどこが拡充されたのでしょうか。ポイントは次のとおりです。
<対象となる株式>
一般措置では、納税猶予の対象となるのは総株式数の3分の2までです。それが特例措置では全株式が対象となります。
なお、全株式が対象になるとはいえ、必ず全株式を贈与、相続しないといけないというわけではありません。あとで触れますが、相続時の遺留分の問題などに備えて、株式の一部は評価額を下げたうえで、後継者が経営者から買い取るといったことも考えられます。
<納税猶予の割合>
一般措置では、贈与税については100%、相続税については80%が納税猶予されます。贈与のほうが有利なのではないかと思われるかもしれませんが、贈与税が猶予された分はその後、相続時に精算されるので、最終的には80%の猶予になります。
それに対し特例措置では、贈与税も相続税も100%猶予されます。相続税の猶予割合が80%から100%になっているのが大きなポイントです。
<後継パターン>
一般措置では、納税猶予が認められるのは、先代経営者から後継者への引き継ぎだけでした(現在は拡充)。また、納税猶予を受けられる後継者は一人だけです。
これに対して特例措置では、複数の株主(親族以外を含む)からの贈与も対象となり、また納税猶予を受けられる後継者は最大3人まで認められます。親族などに分散している自社株を集約する場合や、または兄弟で親の事業を引き継ぐ場合には、大きなメリットとなります。
<雇用確保条件>
一般措置では、先ほども少し触れましたが、事業承継から5年間、従業員の雇用の8割(5年間の平均)を維持することが要件になっています。
この要件を満たすことができないと、その時点で納税猶予されていた税額(利子税を含む)を支払わなければなりません。これまで、この要件がネックになって、利用が増えなかったといわれるほど重要な要件なのです。
特例措置では、同じく事業承継のあと、5年間の平均で8割の雇用維持が必要とされますが、万が一、要件を満たさなくなったとしても、その理由を書いた報告書(※1)を都道府県知事に提出し、その確認を受ければ引き続き納税が猶予されます。これによって、ハードルはかなり下がったといっていいでしょう。
※1 中小企業の経営相談等において専門的知識や実務経験が一定レベル以上の者として国が認定した金融機関、税理士、公認会計士、弁護士等(「認定経営革新等支援機関」と呼ばれる)の意見が記載されていることが条件。
<事業承継が困難になった場合>
この制度を利用し、贈与税や相続税の納税猶予を受けながら、途中で事業承継が困難になり、会社の譲渡や合併、自主廃業した場合、納税猶予されていた税額(利子税を含む)の納付が必要になります。
その場合、一般措置では基本的に、納税猶予された税額をそのまま納付しなければなりません。これに対して特例措置では、売却した価額などをもとに税額を再計算し、それまでの猶予額との差額のみを納付すればよいとされます。
事業を承継して頑張ってきたものの、業績悪化などでやむを得ず事業を断念する場合、その時点での自社株評価額は下がっているはずです。以前の高い評価額で計算した税額をそのまま納付するのではなく、下がった評価額で計算しなおして納税すればいいということで、将来のリスクに対する不安を回避することにつながるでしょう。
<適用期間と申請>
以上で特例措置が有利な点を紹介しましたが、特例措置には適用期間や申請手続きなどがあります。
まず、特例措置は2018年1月1日~2027年12月31日までの贈与や相続に限られます。実質、あと8年ほどです。
また、2018年4月1日~2023年3月31日までに「特例承継計画」を都道府県知事に提出することが必要です。こちらはあと3年ほどしかないので、もし特例措置を利用するのであれば、早く準備を始める必要があります。
なお、特例承継計画とは、事業承継についての基本事項のほか、承継したあと5年間の経営計画や認定経営革新等支援機関(※1参照)による指導・助言の内容などを記載した書類で、一定の書式が用意されています。
3.事業承継税制を利用する際の注意点
このように特例措置が設けられたことで、事業承継税制はかなり使い勝手がよくなりましたが、適用要件はかなり複雑で、安易に考えて利用すると失敗しかねません。利用にあたって注意しておきたいポイントについても、見ておきましょう。
<資産管理会社は対象外>
事業承継税制の対象となる中小企業は、業種によって資本金や従業員数に一定の基準があります。また注意が必要なのは、資産管理会社は対象とならないことです。
資産管理会社とは、有価証券、自ら使用していない不動産、現金・預金など特定資産の保有割合が、総資産の帳簿価額総額の70%以上の会社や、これらの特定資産からの運用収入が総収入金額の75%以上の会社をいいます(ただし一定の事業実態のある会社は除く)。そのため、例えば、不動産賃貸業を行っている持株会社などは難しいとされます。
<経営者と後継者の要件>
事業を引き渡す先代の経営者は、会社の代表者であることはもちろん、一族で会社の株式の50%超を保有し、かつ本人が一族のなかで筆頭株主である必要があります。
一方、後継者についても、会社の代表者になることのほか、一族で50%超、そのなかで筆頭株主(後継者が一人の場合)になることが必要です。
さらに注意しなければならないのは、贈与の場合、後継者は20歳以上で自社の役員に就任してから3年経過していなければならない点です。相続の場合も、相続発生の前に役員になっていなければなりません(被相続人が60歳未満で死亡した場合を除く)。これは、事業承継の準備は早めに着手したほうがいい理由にもつながります。
<猶予が取り消される事由>
途中で納税猶予が取り消される事由が細かく定められており、特に猶予を受けてから5年以内のほうが厳しくなっています。
5年以内の主な取消事由としては次のようなものがあります。
・後継者が死亡または退任(やむを得ない理由を除く)した場合
・一族の議決権が50%以下になった場合
・後継者が一族のなかで筆頭株主でなくなった場合
・対象となった株式を一部でも売却した場合
一方、5年経過後の主な取り消し事由はかなり緩やかになり、後継者が社長(代表者)を辞めても構いません。雇用の8割維持という要件もなくなります。そして、納税猶予の対象となっている税額の一部及び利子税を納付することになります。
<相続時の遺留分>
事業承継税制は、経営者から後継者に対する、自社株の贈与や相続における納税を猶予するものです。
しかし、自社株は先代の経営者が亡くなり、相続が発生すると、基本的に相続財産のなかに含まれ、相続人が複数いれば遺産分割の対象になります。その結果、遺留分の問題が発生するのです。
遺留分とは、相続人に法律上保障された一定の割合の相続財産のことです。亡くなった人(被相続人)は、生前に自分の財産を自由に処分できます。自社株を後継者に贈与することも含まれます。また相続において、遺言により自分の財産を指定した人に渡すことも可能です。
一方で、相続には遺された相続人の生活保障や、亡くなった人(被相続人)の財産形成に貢献した相続人への清算といった面もあります。そこで、配偶者や子ども、場合によっては直系尊属には遺留分といって、一定の財産を請求する権利が認められているのです。
そのため、先代の経営者が生前に事業承継税制を利用して、自社株のすべてを後継者に贈与していた場合、相続においてほかの相続人から遺留分の請求を受ける可能性があります。しかも、遺留分の計算にあたっては、相続時の自社株評価額がベースになります。贈与の時点より自社株の評価額がアップしていると、相当の額になるかもしれません。
したがって、事業承継税制を利用する場合は、後継者以外の相続人の同意を得ておくことが極めて重要になります。自社株の移転で納税猶予(さらには免除)ができても、相続自体でトラブルになると、事業承継そのものが台無しになりかねません。自社株以外の現金や不動産などを用意し、それをほかの相続人が相続できるようにしておくなどの方法を考えておきましょう。
<免除になる条件>
事業承継税制では、自社株の贈与や相続にあたって納税が猶予されます。しかし、「猶予」と「免除」は違います。猶予された贈与税、相続税が最終的に免除されてはじめて、この制度を利用した意味があるといえるでしょう。
贈与税や相続税が猶予されているのは後継者です。後継者の猶予された税額が免除されるのはどのような場合なのでしょうか。
基本的に、後継者が次の後継者に対して、同じ制度(事業承継税制)を使って事業を承継した場合が当てはまります。例えば、創業者から2代目に事業承継したときに猶予された税額は、2代目が3代目経営者に同じく事業承継税制を使って事業承継すれば免除になります。つまり、世代を超えて事業を承継していくことが必要となる点は、よく理解しておきましょう。
なお、会社が事実上の倒産状態になったときにも免除されますが、残念ながら、倒産したのでは事業承継した意味がありません。
また、贈与税の猶予を受けたまま先代の経営者、または後継者が亡くなった場合も免除されます。ただ、先代の経営者が亡くなった場合、贈与税の猶予税額は免除されますが、今度は相続税の猶予対象となるかどうかに移ります。後継者が亡くなった場合も、後継者が猶予されていた贈与税、相続税は免除されますが、後継者が保有していた自社株については相続税の対象となります。
4.事業承継税制のメリット、デメリット
ここでもう一度、事業承継税制のメリットとデメリットを確認しておきましょう。
【メリット】
●自社株の移転にともなう贈与税や相続税の納税が猶予される
●さらに、この制度を利用して事業承継を続ければ免除が受けられる
●自社株の移転にあたり、評価額を下げるなどの対策をする必要がない
●事業承継のための納税資金の心配をしなくてすむ
●特例措置は期間が限定されており、先代の経営者や後継者の間で話を進めやすい
【デメリット】
●納税猶予から免除になるまでの期間が長期に渡る
●納税猶予にはさまざまな取り消し事由がある
●取り消し事由に当たった場合、猶予されていた税額と利子税を払わなければならない
●適用要件などが非常に難解・複雑であり、自力での手続きが困難である
●後継者以外の相続人がいる場合、先代の経営者の相続発生時に遺留分を巡るトラブルにつながる可能性がある
5.まとめ
以前まで、事業承継における株式の移転では、会社の利益を一時的に減らして株価を圧縮したうえで、経営者から後継者に贈与するというやり方がよく見られました。
しかし、事業承継税制を利用すれば、会社の利益を無理に減らすといったことは必要ありません。会社の業績向上や内部体制の整備といった、事業承継に向けて本来やるべきことに集中すればよいといえます。
ただし、相続における遺留分の問題など、株式の移転のみならず、相続全体のバランスに配慮する必要があります。
単に「得だから」「使いやすくなったから」といって安易に利用すると、逆効果になりかねません。事業承継税制は、事業承継における有力なツールであることは間違いありませんが、自社にとってはどのような形で利用するのが適切かどうかは十分な検討が必要です。
事業承継税制の上手な利用ポイント|相続・事業承継|100年企業戦略オンライン : https://100years-company.jp/articles/inheritance/040046
詳細はこちら
プレスリリース提供元:@Press