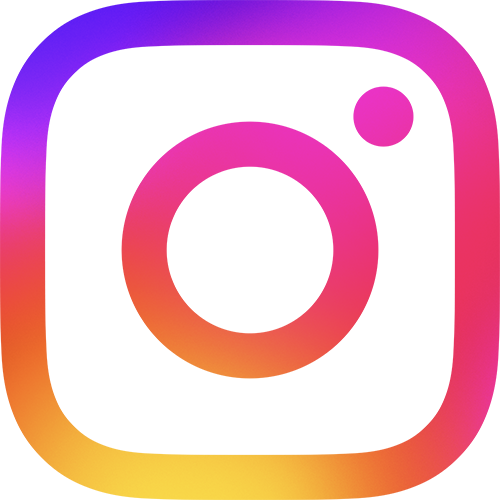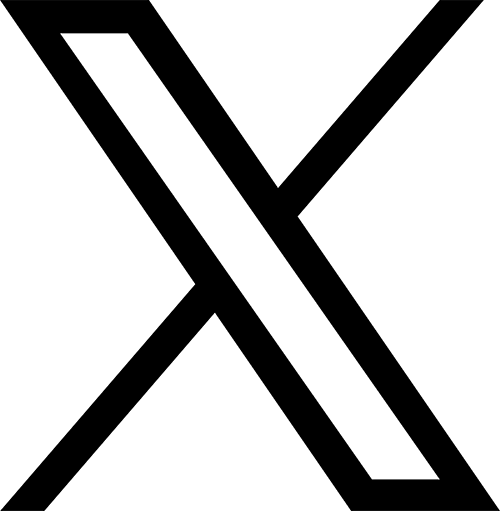ビオチンとは?
ビオチンは、ビタミンB群に属する水溶性のビタミンで、ビタミンHとも呼ばれています。
体内では糖、アミノ酸、脂質などの代謝を助ける補酵素としての役割を持ち、エネルギー生成の補助も担ってくれます。
摂取することで疲労回復が期待できるほか、皮膚や粘膜の維持や爪や髪の健康に至るまで身体の美容と健康に深く関わっており、皮膚の炎症を防止する働きがあります。
ビオチンの美容と健康への効果

肌・髪・爪などの健康維持
ビオチンは皮膚や粘膜などを維持し、爪や髪の毛の健康を保つ働きをしてくれます。
ビオチンの摂取量が髪の量や太さに影響するという報告もあるそうで、髪に必要な栄養を与えてくれる効果が期待できます。
疲労回復
疲労の原因の一つは「体のエネルギー不足」です。エネルギーが不足すれば疲労をより強く感じるようになりますし、疲労回復も遅くなります。
エネルギー生成をサポートする働きのあるビオチンを摂取すれば、疲労回復に繋がります。
皮膚炎や口内炎の改善
これらの炎症の原因の一つとして、ビオチン不足が挙げられます。
ビオチンには皮膚や粘膜を維持し、炎症を防止する働きがあります。
また、ビオチンは皮膚の炎症やかゆみの原因となる「ヒスタミン」の生成を抑制する効果もあるため、ビオチンを摂取することで皮膚炎や口内炎などの防止と改善が期待できます。
ビオチンの不足について

ビオチンが不足すると、皮膚炎、結膜炎、舌炎、知覚過敏、脱毛、白髪の増加などの症状が出る場合があります。
また、リウマチ、シェーグレン症候群、クローン病などの免疫不全症のほか、インスリンの分泌能が低下し糖尿病のリスクが高まる可能性があるとされています。
とはいえビオチンは含まれている食品が多く、また腸内細菌によっても生成されているため通常の食生活をしていれば欠乏することはあまりないと言われています。
ただし、いくつかの条件に当てはまる場合にビオチンが欠乏することがありますので注意しましょう。
ビオチンが欠乏しやすいと言われている条件下
・生の卵白を多量に長期間にわたり摂取した場合
・抗けいれん薬を長期間使用している場合
・長期間頸静脈栄養法を行なっている場合
・極端に食事制限を行なったり、偏食がある場合
・慢性的に下痢症状がある、長期間抗生物質を使用している場合
など
上記の場合はビオチンが欠乏する可能性が高いと言えますので、もし不安がある場合は医師に正しい指示を受けて改善していくことをお勧めします。
ビオチンの効率的な摂取方法

ビオチンはどのように摂取するのが良いのでしょうか?
いくつかの摂取方法をご紹介します。
食材を通して摂取する
ビオチンはきのこ類、肉類、種実類、卵類、魚介類に特に多く含まれています。
ただし、卵に関しては卵白中のアビジンという物質がビオチンと結合して吸収を妨げてしまうため欠乏しやすいです。加熱すれば問題ないですが、生卵を大量に食べるのはむしろ逆効果となってしまいますので注意しましょう。
尚、ビオチンは調理によって分解されにくい性質がありますので、摂取において調理方法に気をつける必要はあまりなく、取り入れやすい栄養素であることも特徴です。
ビオチンを多く含む食品の成分量目安(可食部100gあたり)
レバー:76~230㎍
卵黄:65㎍
ナッツ類:60~96㎍
きくらげ:27㎍
あさり:23㎍
アンチョビ:22㎍
ししゃも:18㎍
乾しいたけ:41㎍
サプリメントからの摂取
ビオチンの摂取はサプリメントからも可能です。
水溶性のビタミンなので、服用しても2〜3時間で体外へ排出されてしまいます。そのため、一度に摂取せず1日のうち数回に分けて摂取するのが良いでしょう。
1日の摂取目安量
摂取目安量については男女差は示されておらず、1〜5歳は20㎍/日、6〜9歳は30㎍/日、10〜11歳は40㎍/日、12歳以上は50㎍/日が目安とされています。
また、過剰に摂取しても排出されるものになるので、用量以上の摂取は意味がありません。過剰な摂取は避け、必要量を摂取するようにしましょう。
まとめ
今回はビオチンについて解説しました。肌や髪などの維持にとても大切な栄養素であるほか、エネルギー生成を助ける働きなど健康にとっても非常に重要な存在であることがわかりました。
比較的摂取しやすい栄養素であるため、目安の摂取量を安定して摂ることができているか改めて意識してみると良いでしょう。